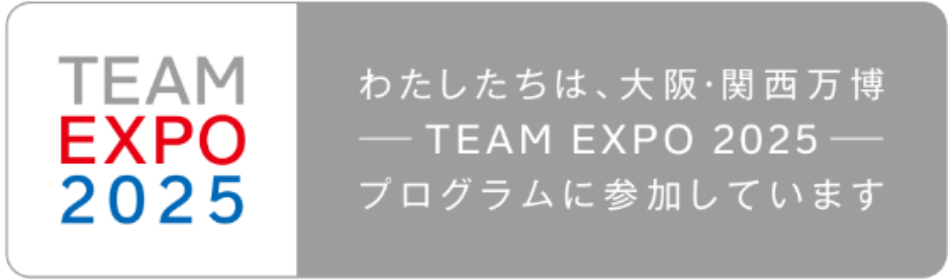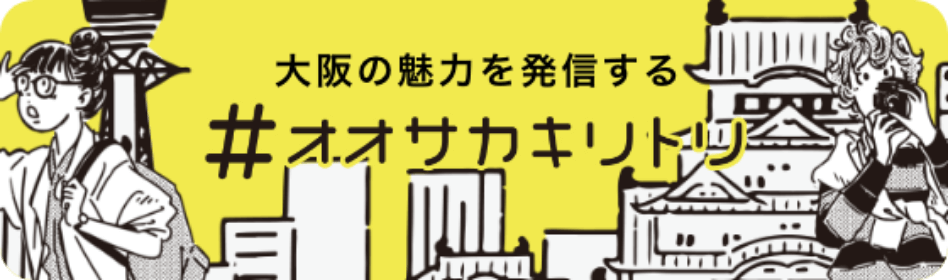夜の京都を活性化させる、ナイトタイムを活かした新たな価値の創造
CLIENT : 京都市- 自治体
- マーケティング
- 観光ビジネス

OVERVIEW プロジェクト概要
「文化首都としての京都の夜の魅力創出」を目的とした、シンポジウムおよびワークショップの企画運営です。シンポジウムで京都ならではの新たな夜の価値を見出す機運醸成を図り、文化芸術をはじめとする様々な分野で活躍する人々が交流するワークシップの開催では意見を集約し具体的な施策に繋げ、また、意見を冊子にまとめました。
POINT プロジェクトのポイント
- 京都発の全国に向けたナイトタイムエコノミーの起点づくりを実現
- 人選や場所にもこだわり、継続的な機運醸成にも活かせるよう冊子化
プロジェクト担当者 京都支社K.Tさん
大学卒業後入社、京都支社にて一般企業、行政、学校関係などの広告、販促施策、動画制作、イベント企画運営など幅広く担当。営業としてクライアント対応、社内チームのディレクター的立場で業務に取り組み、時には企画、セールス、実行までを一手に担う。
文化的側面から夜の京都を盛り上げる足がかりに
- ──京都の夜を文化的に楽しむイメージですが、目的や全体像をお聞かせください。
- 文化庁が京都へ移転してきたことを契機に、文化首都としての夜のあり方を創出するというのが目的です。文化、観光、まちづくりといった分野を横断して進められています。京都は夜に出かける文化的な場所がほとんどないというのが実情です。しかし、探せば夜に活用できる場所がもっとあるはず。そこで、そういった場所を活かし、皆で話し合いながら夜の魅力や価値を創造し、文化的に京都をさらに盛り上げていこうというきっかけとなるシンポジウム&ワークショップを開催するというのが、今回のプロジェクトでした。機運を高める第一歩という位置づけですね。その上で企画運営、およびそれらに関する広報活動を行いました。
- ──ナイトタイムエコノミーの推進において京都の抱える課題は何ですか?
- 昼間は寺社仏閣や美術館をはじめとする観光スポットが多いものの、夜に行く場所がほとんどないという点です。例えば、美術館なども、閉館時間の延長を試みたこともありましたが、経費と集客が見合わなかったようです。単独の施設だけで夜間営業を行っても、集客は難しいかもしれません。それを定着させる時間も必要ですし、継続的に予算を投じ続けることができるのかという問題もあります。そのような状況もあり、夜の経済活動「ナイトタイムエコノミー」をどのように活性化させるかがポイントになってくるのです。


- ──そのためのシンポジウムとワークショップなのですね、それぞれの内容は?
- シンポジウムは「京都から日本の夜の価値創造を考える」と題し、大江能楽堂で開催。文化界、経済界のトップリーダーとして当時の京都市長、文化庁長官、華道の次期家元、女性経営者にご登壇いただき対談を行いました。さらに参加者アンケートを実施しました。
ワークショップは元毎日新聞社京都支局で京都市登録有形文化財にも指定されているビルの地下などで開催いたしました。1日目に行ったのは、「YOASOBI CARD(ヨアソビカード)ワークショップ」です。グループに分かれ「動詞+場所」というテーマで、読む、書くなどの動詞カードと路地や川沿いなどの様々な場所カードをランダムで引きます。メンバー同士で組み合わせてどんな活動やコンテンツが作れるかを発表し合い、最も実現したいアイデアを深堀し、チャットGPTに入力して画像を生成、雰囲気を見るという試みで大変好評でした。
2日目は「日本の夜の価値創造ワークショップ」と題し、各都市の文化活動や観光に関わる行政、市役所の方々をお招きして開催しました。夜の価値が発信されている事例紹介や、ポテンシャルを秘めている場所について発表。より実践的で実現に近い内容でした。最終的にはそれらを詳細な報告書として54ページの冊子にまとめ、さらにデジタルブックとしても制作。表紙デザインは、京都芸術大学の学生の方々が手掛け、産学連携的な流れが生まれた点も良かったです。
- ──この案件で特に苦労した点と、そこから学ばれたことをお聞かせください。
- 今事業は文化庁、京都市、ナイトタイムエコノミー推進協議会と関係部署が多岐に渡る為、本番に向けての調整事が多く、細部にわたる見直しが必要だった点です。弊社に情報が下りてくるまでも、行政担当部署間の調整なども多くあったかと存じます。チームとして各セクションが密に連携することで事業を遂行できました。やはり、一つの事業を進める上で、人と人との繋がりや先を見越す力が非常に重要であるということを感じましたね。